重要文化財「御本殿」大改修および「楼門」「回廊」等改修事業
 御祭神・菅原道真公の御墓所の上に建つ重要文化財「御本殿」は、天正19年(1591)に筑前国主小早川隆景によって再建されました。重厚な唐破風をもつ檜皮葺きの大屋根、細部にまで施された漆塗り・金箔・彩色や華やかな装飾など、安土桃山時代の豪壮華麗な建築様式を今に伝える貴重な建物です。また道真公の御神霊が永久に鎮まる御本殿に繋がる回廊や楼門も檜皮葺きで覆われており、その格調の高さを物語っています。しかし自然素材でつくられた木造建築ゆえに、気候や自然の影響を受けやすく、各時代の人々の手による丁寧な修繕と維持を経て今日まで受け継がれてきました。
御祭神・菅原道真公の御墓所の上に建つ重要文化財「御本殿」は、天正19年(1591)に筑前国主小早川隆景によって再建されました。重厚な唐破風をもつ檜皮葺きの大屋根、細部にまで施された漆塗り・金箔・彩色や華やかな装飾など、安土桃山時代の豪壮華麗な建築様式を今に伝える貴重な建物です。また道真公の御神霊が永久に鎮まる御本殿に繋がる回廊や楼門も檜皮葺きで覆われており、その格調の高さを物語っています。しかし自然素材でつくられた木造建築ゆえに、気候や自然の影響を受けやすく、各時代の人々の手による丁寧な修繕と維持を経て今日まで受け継がれてきました。
来る1125年式年大祭に向け、先人たちより預かった大切な御社殿を未来に継承すべく、124年ぶりとなる御本殿の大改修をはじめ、楼門・回廊の檜皮葺き替え工事を行います。
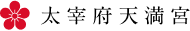





 檜皮と檜皮を留める竹釘 一枚一枚手作業で葺きます。
檜皮と檜皮を留める竹釘 一枚一枚手作業で葺きます。
 漆を一層ずつ掻き落とし、残せるところ、補修すべきところを判断しつつ、約30行程に及ぶ作業をすすめていきます。
漆を一層ずつ掻き落とし、残せるところ、補修すべきところを判断しつつ、約30行程に及ぶ作業をすすめていきます。
 御本殿に取り付けられていた約800点の飾り金具はすべて取り外し、京都にて補修を行っています。
御本殿に取り付けられていた約800点の飾り金具はすべて取り外し、京都にて補修を行っています。
 苔が一面に繁茂し、一部檜皮が剥がれ落ちてしまった回廊屋根。御本殿工事完了後、楼門・回廊の檜皮葺き替え工事を進める予定です。
苔が一面に繁茂し、一部檜皮が剥がれ落ちてしまった回廊屋根。御本殿工事完了後、楼門・回廊の檜皮葺き替え工事を進める予定です。
 近年の
近年の
 太宰府天満宮は「天神の杜」と呼ばれる樹齢
太宰府天満宮は「天神の杜」と呼ばれる樹齢 太宰府天満宮では1125年大祭に向けて取り組む様々な文化事業の一つとして、明治35年(1902)の1000年大祭を記念して建てられた近代和風建築「文書館」のための24面の襖絵を日本画家・神戸智行に依頼しました。
太宰府天満宮では1125年大祭に向けて取り組む様々な文化事業の一つとして、明治35年(1902)の1000年大祭を記念して建てられた近代和風建築「文書館」のための24面の襖絵を日本画家・神戸智行に依頼しました。